金属元素は、
化学触媒であると同時に、
生物触媒であることを疑問の出発点として考えることが大切だと考えている。
少し「なにかを加える」だけで、
未知の、
そして神秘の世界が広がっていくに違いない。
(本書「エピローグ」より抜粋)
記事冒頭から「元素」および「金属」への愛が溢れて、エンジン全開だ♪
ん? 暑苦しいって? そんな文句は知らん(笑)
以前に「元素」への全力の愛を記事↓で表現(?)したことがあります故。


本記事では、そこで紹介した書籍の著者である桜井 弘先生の新著↓を紹介しよう♪
まず、ブログ主が考える本書の結論から述べよう。
生命の誕生から生物進化への長い道のりにおいて、
金属元素が数多くの影響を与えてきたことが示唆されている。
例えば、
我々の生命の営みにおいて重要な役割を果たしているミトコンドリア内では、
鉄や硫黄を含む数種類のタンパク質や銅イオンで構成されたシステムを通じて、
生体内のエネルギーを産生している。
21世紀も最初の4分の1が経過し、
生命のあり方
生命の起源と進化
健康や医療
…これらと金属に関する研究は跳躍的な進歩を遂げてきた。
豊富なデータや貴重な考え方も多数蓄積されてきている。
しかし、まだまだ解明されていない多くの疑問が残されている。
以下、主だった謎を生物進化の道程順に挙げていく。
①生命の始原物質…アミノ酸, 単糖, 脂肪酸, コレステロール, 核酸塩基, ビラミン類など…
これらの合成に金属元素はどのように関与したか?
②アミノ酸が重合して生成されるペプチドやタンパク質の合成に
金属元素はどのように関与したか?
③細胞をつくるさまざまな粒子や細胞の合成に
金属元素はどのように関与したか?
④単細胞が接着して多細胞生物が登場する際に
金属元素はどのように関与したか?
⑤生命をつないでいく遺伝子の誕生に
金属元素はどのように関与したか?
⑥多細胞から成り立つ複雑で多様な生物個体の登場に
金属元素はどのように関与したか?
⑦生物の進化の過程で、金属元素はどのように関与してきたか?
そして、未来の生物進化に、金属元素はどのように関与していくだろうか?
…つまり、生命にとって金属とはなにか? (タイトル伏線回収(笑))
本書は、永遠の課題とも思えるこれら難問に応えるために、生命と金属について蓄積されてきた知識の拠りどころとなることを願って刊行されている。
ではでは、そんなおすすめ書籍の中で、ブログ主激推しのトピックを紹介していこう!!
完全金属騒乱!! 乞うご期待!!
生命進化を推進した金属イオン
生命の誕生へといたる長い道筋には、次のような各ステージが存在していたと考えられる。
原始生命低分子の合成、原始生命高分子の合成、膜様物質の合成、エネルギー産生物質と産生系の合成、遺伝子の合成、単細胞の合成、多細胞の合成…etc.
これら多岐にわたる重要な研究が、さまざまに模索されながら着々と進められている。
そうした一連の生命合成への道は、現在では海洋中で進行したと考えられている。
そして各ステージには、たえず金属イオン、特に微量元素(後述)の関与が必要だっただろうことが理解されてきた。
ここで、生命が微量元素を巧妙に用いている例を紹介しよう。
<銅イオン>
まだ酸素分子が少なかった時代の海洋には、
太陽からの強い紫外線や各種の宇宙線(高エネルギーの放射線)が降り注いでいた。
たとえば、
放射線が水と反応すると、
ヒドロキシルラジカル(・OH)や水素ラジカル(・H)が生成される。
生成された2個のヒドロキシルラジカルは、
さらに反応して過酸化水素(H2O2)をつくり、
また、
酸素分子があれば水素ラジカルと反応してスーパーオキシドアニオンラジカル(O2-)を生み出す。
スーパーオキシドアニオンラジカルは水中の水素イオン(プロトン、H+)と反応して過酸化水素となる。
このようにしてつくられた活性酸素種は反応性がきわめて高く、
生命にとって有害な作用を及ぼす。
そのため、
生命がつくられ、
その活動を維持していくためには、
これら活性酸素種をさまざまな段階で消去する必要がある。
ここに、
微量元素が大きな任務を果たすチャンスが生まれたのである。
銅イオン(Cu2+)にはそもそも、
単独でもスーパーオキシドアニオンラジカルを消去する能力が備わっている。
そこで、
銅イオン単独の場合の活性酸素種消去能力と、
銅イオンを含みスーパーオキシドアニオンラジカルを消去するための特異的酵素である、
スーパーオキシドジムスターゼ(SOD)の活性酸素種消去能力を比較してみよう。
(実際に、
生体内で銅イオンが単独で存在することはなく、
たいていはタンパク質などと結合している。)
詳細は本書↑を読まれたしだが、
銅イオン単独の場合に比べ、
SODはその2000倍という驚くべき活性が現れる。
SODがスーパーオキシドアニオンラジカルを消去するための特異的な酵素である所以だ。
天然のSODがこれほど高い活性を示すためには、
タンパク質が基質(酵素作用を受けて反応する物質)のO2-を化学的に認識して捕獲し、
さらにそのO2-を反応触媒部位である銅イオンまで迅速に輸送しなければならない。
加えて、
この反応によって生成される過酸化水素と酸素分子を、
タンパク質の外に搬出する必要もある。
このような高度な機能を的確に発揮するには、
タンパク質のアミノ酸配列と、
その高次構造の形式がきわめて重要であると推定され、
生命現象を支える精緻なメカニズムがはたらいていることがよくわかる例である。
<鉄イオン>
過酸化水素を消去・分解する金属酵素であるカタラーゼの活性中心にはヘム鉄があり、
その中心には鉄イオンが存在する。
鉄イオン(Fe3+)は、
過酸化水素(H2O2)を酸素分子と水に分解する作用をもっている。
この反応速度は10-5/mol/秒である。
鉄イオンの代わりに低分子のヘム鉄錯体を用いて反応速度を測定すると、
10-2/mol/秒となり、
触媒活性は1000倍となる。
そして、
過酸化水素を得意的に分解する酵素であるカタラーゼを鉄イオンの代わりに用いると、
反応速度はじつに105/mol/秒となり、
触媒活性は鉄イオン単独の場合に比べて1010倍と著しく増大する。
この例においても、
カタラーゼが過酸化水素を化学的に認識・捕獲し、
触媒活性点であるヘム鉄のFe3+まで高速に輸送して反応を進めたうえで、
反応後は速やかに酸素分子を水をタンパク質外に排出するシステムが築かれている。
人類が積み上げてきた科学はまだ、
このような高精度かつ高速に進む酵素反応の機構を解明できていない。
これら例が示すように、ある種のタンパク質と結合することで金属イオンの能力を飛躍的に高めることができる。
海洋中で生命の原型…たとえば原核生物など…がつくられる過程では、多数の金属イオンがさまざまなタンパク質と結合して多様な形に組み立てられ、驚異的な生理的機能を獲得し、進化を推し進めていったのではないかと推定される。
必須微量金属
詳細は本書↑を読まれたしだが、1800年代後半から進められてきた各研究により、鉄を含む酸素運搬タンパク質「ヘモグロビン」の全体像が明らかにされていくなかで、このタンパク質は哺乳動物以外の血液中にも発見され、生物界に広く存在することがわかってきた。
さらに、ヘモグロビンの生合成には、鉄のみならず、銅や亜鉛といった金属イオンも必要であることが判明した。
これは、じつに興味深い事実であり、生命を維持・構成する生体機能が、きわめて精緻かつ複雑なものであることが認識される契機ともなった。
現在では、人を含む生物が生きていくうえで、多数の金属元素が必要不可欠であることが、長い研究の蓄積から明らかにされている。
これらは体内ではごく微量しか検出されないため、「生体必須微量元素」とよばれている。
ヘモグロビンの生合成に必要な鉄, 銅, 亜鉛の他に、マンガン, セレン, モリブデン, クロム, コバルトなども生体必須微量元素として知られている。
さらに、必須かもしれない微量元素として、鉛, スズ, ニッケル, バナジウムなどがある。
<「微量」とはどのくらいの量?>
生体内の各元素は幅広い濃度範囲で存在しており、
分析化学で用いられる濃度範囲では次のように分類される。
①多量元素 (major elements):1%以上
②少量元素 (minor elements):1~0.01%
③微量元素 (trace elements):0.01~0.0001%
④超微量元素 (ultratrace elements):0.0001%以下
重量濃度(元素の質量/試料の重量)で表すと、
微量元素は1~100ppm(100万分の1:1μg/g)の濃度範囲となる。
超微量元素には、
ppm以下の濃度で存在している元素も多くあり、
それらの濃度はppb(10億分の1:1ng/g)やppt(1兆分の1:1pg/g)で表される。
私たちの生体内には、
マイクログラムからピコグラムに及ぶきわめて広範囲にわたって、
性質の異なる多数の金属元素が含まれている。
生きていくため、
健康を維持するためとはいえ、
これほど多様な金属元素を必要とする理由はなんだろうか?
この謎は、
残念ながら未だはっきりと解明されていない。
<必須微量金属元素リスト> 現在までに判明している必須微量金属元素を簡単に紹介していこう。 ① 鉄 鉄はヒトの体内に4~6gが存在する。 亜鉛の2倍以上、 銅の60倍以上であり、 金属元素のなかでは最大量を誇っている。 体の中の鉄のほとんどはタンパク質を結合しており、 その約65%がヘム鉄タンパク質として、 酸素分子の運搬を担うヘモグロビン中に存在している。 約15~30%は非ヘム鉄タンパク質のフェリチンやDNA結合フェリチン、 フラタキシン類などの貯蔵鉄として、 そして約5%が筋肉中にヘム鉄タンパク質のミオグロビンとして存在している。 ヘム鉄タンパク質はヘム構造の中心に鉄をもち、 酸素分子の貯蔵や運搬などの生命にとって最も重要な機能に関わっている。 一方、 非ヘム鉄タンパク質では、 電子伝達, 生体エネルギー産生, 細胞内代謝や細胞応答、 それらに関わる種々の酵素の活性中心に鉄が存在していて、 サイトカインやホルモンなどの多くの生体分子の活性化機構やシグナル伝達機構に 重要な役割を果たしている。 さらに、 スーパーオキシドジムスターゼ(SOD)やカタラーゼなどの 抗酸化酵素の活性中心にも存在しており、 酸素代謝や抗酸化反応にも関わっている。 ② 亜鉛 亜鉛は体重70kgの人では総量2~3gが含まれている。 この量は鉄の約2分の1、 銅の約30倍以上、 そしてマンガンの約100倍以上である。 亜鉛は特に前立腺に高濃度に存在することが知られている。 続いて骨, 腎臓, 筋肉, 肝臓, 心臓, 消化管, 脳, 睾丸, 卵巣に分布している。 亜鉛はホメオスタシスにおいて重要な役割を果たしている。 特に亜鉛欠乏は、 細胞内代謝や細胞応答に関与するそれぞれの活性化機構やシグナル伝達に影響し、 脳神経系, 免疫系, 内分泌系, 消化器系, 循環器系, 栄養代謝系など、 さまざまな領域の機能障害を引き起こす。 さらに遺伝情報の転写に関わる因子として、 亜鉛フィンガータンパク質が知られている。 指を丸めたようなループ構造をもち、 ループの基点で亜鉛が結合して安定化するユニークな構造をもっている。 膵臓中の亜鉛は、 インスリンの生産や機能に関与している。 ラットやモルモットでは膵臓中の亜鉛はほとんどランゲルハンス島に濃縮されている。 さらに膵臓の亜鉛濃度はランゲルハンス島の細胞の機能状態によって変化することや、 亜鉛がインスリンを生産するβ細胞の機能に関与することが知られている。
③ 銅
銅の濃度は肝臓中で最も高く、
次いで脳組織に多い。
血中の銅はおもに2つの形で存在している。
一つは、
タンパク質に強固に結合している「セルロプラスミン」とよばれる青色銅タンパク質である。
セルロプラスミンは、
多くのポリフェノールやセロトニンなどの生理活性物質を含む、
種々の基質を酸化する酵素である。
人では血漿中の銅の約80%がセルロプラスミンとして存在している。
残りの約20%の銅は、
血清アルブミンとゆるく結合していると考えられている。
アルブミンと結合している血漿銅が実際の銅輸送を構成している。
銅イオンは各種の酸化還元酵素の活性中心にあり、
種々の生理作用や機能に加え、
電子伝達などの維持に関わっている。
④ マンガン
マンガンの必須性は、
軟骨のムコ多糖類の合成にマンガンが特有の作用をもつことから明らかにされた。
一方、
マンガンは肝臓の糖新生にも関与し、
正常な糖代謝に重要な役割を果たしている。
ミトコンドリア中のマンガンを含むピルビン酸カルボキシラーゼはピルビン酸のカルボキシル化を触媒し、
オキサロ酢酸を生成する反応を触媒している。
マンガンは鉄と同様にトランスフェリンと結合し、
血液循環によって肝臓を経由して、
腎臓, 脳下垂体, 甲状腺, 副腎, 膵臓などの多くの組織に輸送されている。
マンガンはさらに、
骨形成時のプロテオグリカン合成に重要なグルコシルトランスフェラーゼ、
抗酸化作用をもつSODなどの金属酵素の活性中心に存在し、
生体機能に重要な役割を果たしている。
⑤ セレン
セレンは栄養素として至適濃度範囲が狭い元素であり、
体内でのふるまいはセレンの血中濃度によって著しく変化する。
セレンが充足した状態では肝臓や腎臓に輸送された後、
すみやかに排泄される。
セレン欠乏状態では精巣や甲状腺など内分泌器官に優先的に分布する。
生体内に吸収されたセレン化合物は、
最終的にセレナイドに代謝され、
セレノプロテインPなどのセレン含有タンパク質に取り込まれて「セレノシステイン」として存在する。
セレンはまた、
グルタチオンペルオキシダーゼやチオレドキシン還元酵素などの抗酸化酵素、
あるいは甲状腺ホルモンの代謝に必要な脱ヨード化酵素の構成成分として存在している。
セレンの欠乏は心筋症を起こし、
中国では克山病の原因となった。
セレンの過剰は、
神経症状, 胃腸障害, 成長障害, 爪の変色と脱落, 脱毛などの症状を起こす。
⑥ モリブデン
モリブデンは食品からモリブデン酸イオン(MoO42-)の形で吸収され、
血中に入って肝臓, 腎臓, 脾臓, 肺, 脳, 筋肉に分布する。
体内のモリブデンのほとんどは、
アミノ酸代謝酵素, 核酸代謝酵素, 硫酸代謝酵素などの酵素の活性中心に存在する。
糖質や脂質の代謝に関与して、
貧血を予防するはたらきを担っている。
モリブデンが欠乏すると、
息切れ, 心拍数の増加, 悪心, 嘔吐, 昏睡などの症状を引き起こす。
⑦ クロム
食品から摂取された6価クロム(Cr6+)は、
小腸から吸収され、
赤血球膜を通過して、
赤血球内で3価クロムイオン(Cr3+)に還元されてヘモグロビンと結合する。
しかし、
Cr3+は赤血球膜を通過できないため、
血漿中のアルブミンやトランスフェリンと結合し、
肝臓や腎臓へ運搬される。
人では60~70%がアルブミン、
30~40%がトランスフェリンと結合している。
おもな生理的役割は、
糖代謝, コレステロール代謝, コラーゲン形成, タンパク質代謝などが知られている。
クロムの欠乏はグルコースや脂質, タンパク質の代謝などに幅広い障害を与える。
⑧ コバルト
コバルトは食品から、
2価コバルト(Co2+)または3価コバルト(Co3+)の状態で腸管から吸収される。
体内のさまざまな組織に分布するが、
特に肝臓, 腎臓, 骨に比較的多く分布する。
ビタミンとしては唯一コバルトイオンを含むビタミンB12(シアノコバラミン)は、
神経組織の健康維持, 赤血球や核酸の合成に必須である。
コバルトの欠乏は、
悪性貧血, メチルマロン酸尿症, 食欲減退, 体重減少などを引き起こす。
金属元素を含む医薬品
20世紀の後半以降は、新しい有機合成医薬品や天然物医薬品が続々と登場し、それに伴って無機系医薬品の研究も世界的に活発となった。
そして、天然物や合成有機化合物などでは決して得られない生理・薬理的効果が発見され、医薬品を創製する新しい学問として発展している。
<代表的な無機系医薬品>
発見の契機や作用機序は本書↑を参照されたし。
ん? 説明をサボるなって?
記事ボリュームもすごいことになってきているのでお許しを(笑)
① 白金を含む抗がん剤
シスージアミンジクロロ白金(Ⅱ)錯体 (シスプラチン)
第3世代の白金錯体 (オキサリプラチン)
② リチウムを含む双極性障害・統合失調症薬
炭酸リチウム (リーマス)
③ ヒ素を含む急性前骨髄球性白血病治療薬
三酸化ヒ素または亜ヒ酸 (トリセノックス)
④ 亜鉛を含むウィルソン病(肝レンズ核変性症)治療薬
酢酸亜鉛水和物 (ノベルジン)
⑤ 鉄を含む高リン血症治療薬
クエン酸第二鉄水和物 (リオナ)
⑥ ビスマスを含むヘリコバクター・ピロリ菌感染治療薬
次サリチル酸ビスマスⅢ
⑦ 銅錯体:胃の粘膜を修復する作用
銅ークロロフィリンナトリウム (サンクロン)
銅ークロロフィリンカリウム (サクロン)
⑧ アルミニウム錯体:胃酸抑制薬・胃の粘膜保護作用
ショ糖硫酸エステルアルミニウム塩 (アルサルミン、スクラルファート)
⑨ 亜鉛錯体
亜鉛ーカルノシン錯体 (ポラプレジンク、プロマック):胃潰瘍治療作用
ヒスチジン亜鉛水和物 (ジンタス):低亜鉛血症治療薬
なお本書では、金属元素を用いた診断用・治療用放射性医薬品も紹介されている。
本記事では、ブログのボリュームおよびブログ主の専門性(職業柄、「軽く」程度の紹介なんてできないってばよ)を鑑みて、泣く泣く割愛とする。悪しからず。
興味のある方は本書↑、および↓の記事で紹介されている書籍を読まれたし。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最後にもう一つ本書内で取り上げている「元素」の話題をば。
新たな元素は、
今度もさらに合成されていく可能性はあるのだろうか?
(ブログ執筆時点では118番元素であるオガネソンまで合成されている。)
すでに119番や120番元素の合成が試みられている。
さらにどれくらいの元素が合成されうるかについては、
フィンランドの理論化学者ペッカ・ピューコックによって計算されている。
その結果によれば、
じつに172番元素までが合成可能なのだという。
なお50を超える元素がわれわれの前に姿を現す可能性がある!!
今後の合成研究の発展が期待される。
金属はすごい!! (いつか…完全金属騒乱もブログで取り上げたいなぁ…(笑))
ありきたりな表現であるが、その言葉の重みを改めて感じる今日この頃。
もっと知りたいと思ったら、専門書を詰め込んで、「理学の頂」の山登りに出かけよう。
目指せ!!理学の友人(笑)!!これぞ賢者への道程!!
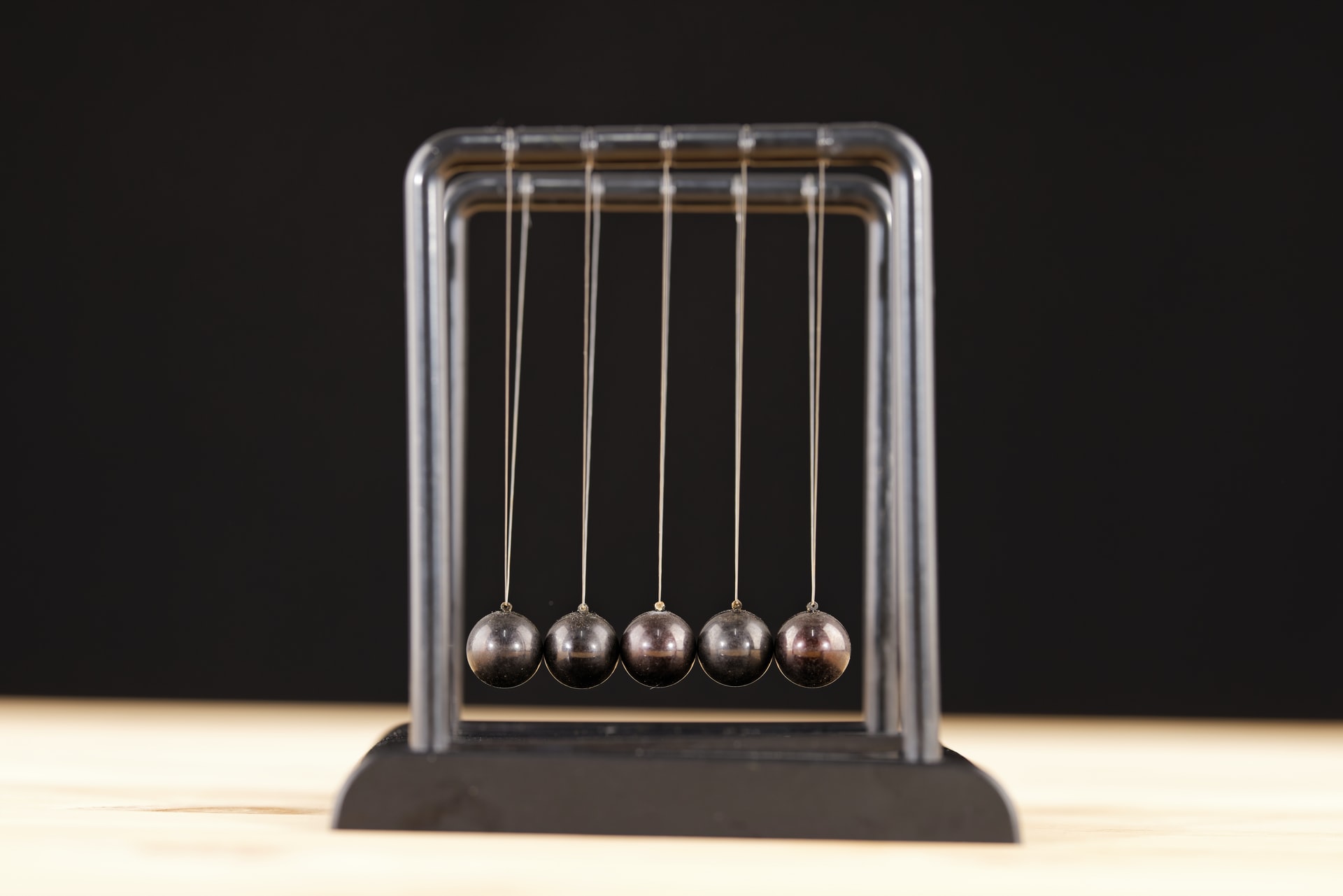


コメント