「経済」とは貿易の科学であり、すべての人間を満足させるに足る量がない場合の貨幣・モノ・サービス・その他資源の流れを司る。 他の分野の科学者は経済学のことをふざけて「陰気な学問」と呼んだりもする。 経済学者は経済学を「ミクロ経済学」と「マクロ経済学」の2つに大別する。 ミクロ経済学は企業や家庭といった小さな構成単位における経済学を扱う。 マクロ経済学はより大きな視点で、経済成長や国の豊かさといった分野を扱う。 世界のマクロ経済学で現在優勢なのは「資本主義」であり、これは企業がモノやサービスを作り上げ、販売し、得られた利益が企業の持ち主へと還元される仕組みのことである。 これによって持ち主の資本が増加すると、資本を投入して資産やサービス(労働者)を購入できるようになり、それによりさらなる富が生まれる、という構造だ。 資本主義の反対は「共産主義」で、得られた利益は労働者間で均等に分配される。 (参考:いつもの↓。バジリスクの牙を突き立てたらブログ主は……泣きだす(笑))
近代ならスミス・ケインズ・マルクス…、現代ならピケティ・ディートン・アカロフ…etc.
代表的な経済思想を手軽に、わかりやすくて面白く、ざっと知ることができる!!
本記事で紹介する書籍↓(↑は残像だ(笑))は、そんなコンセプトで経済学の名著50冊の要点を整理し、教養として経済学を楽しめ、ビジネスシーンで活用する足掛かりになる一冊。
作者は某予備校で公民担当の名講師。以前の記事でもそうだが、やはり教える・伝える側のプロのわかりやすさは段違いだな。ブログ主はそこにシビれる! あこがれるゥ!
本業との兼ね合いでお忙しいところ、陰気な学問(笑)の中でも辞書並に分厚い名著の数々を悪戦苦闘しながら読破し、その経済学的思考回路を↓の構成でまとめてくださった作者に感謝の正拳突き1万回(笑)
① 「経済学」の基本が分かる名著13冊 そもそも経済学って何?
② 経済発展と自由主義が分かる名著13冊 人間は経済をコントロールできるのか?
③ 「資本主義」が分かる名著13冊 経済学を考える上で欠かせない最重要テーマ
④ 「豊かさ」と「貧困」が分かる11冊 経済学は「格差」をどう考えるか?
前々記事(哲学の名著)・前記事(社会学の名著)で流れはもうわかったよね?(笑)
それではブログ主チョイスで、「どこが陰気な学問じゃい!」と衝撃を受けた、センセーショナルな名著を紹介していこう。
「アニマルスピリット」 (2009) ジョージ・アーサー・アカロフ/ロバート・ジェイムズ・シラー
2008年のリーマン・ショックが「大恐慌の再現」となってしまったのは、経済学者と政府が、世界恐慌時にケインズが示唆したメッセージを忘れ、独善的になってしまったからだ。
そのメッセージこそが「アニマルスピリット」であり、人間の心理に潜む「合理的でないすべてのもの」のことだ。
本書によると、アニマルスピリットには5つの側面がある。
① 安心: 社会に蔓延すると経済をイケイケにさせ、失われるとパニック状態に陥らせる ② 公平さ: 欠如すると「安心」を崩してしまう危険性がある ③ 腐敗と背信: 悪い動機を持つ経済活動で社会に悪影響をもたらす ④ 貨幣錯覚: インフレ・デフレ等の正しい認識ができなくなる ⑤ 物語: 国民全体が1つの物語を共有すると市場を動かす大きな力になる
経済学はいつの頃からか「科学」を目指し始めた。科学である以上、すべてに合理的な説明が求められる。
となると、合理的に説明がつかない要素は「ノイズ」だ。ノイズは排除しないといけない。
そこで既存の経済学は、こぞってケインズの「一般理論」の角を削り、あろうことかノイズを根絶やしにしてしまった。
そのせいで現代の標準的な経済理論は、洗練されてスマートになったが、肝心の部分が欠落した、非常に不完全な代物になってしまったのだ。
しかしアニマルスピリットは、ノイズなどいう言葉で切り捨てていいほど微細なものではなく、人々の多くの行動を決定づける、「無視できない」要素なのである。
本書では、上記5つの側面を説明したうえで、
「なぜ不況は起こるのか?」 「なぜ未来のための貯蓄はいい加減か?」 「なぜ黒人には特殊な貧困があるか?」 …etc.
↑のような8つの質問に対し、すべてアニマルスピリットを軸に答えている。
本書を読めば、いかに人間が弱く、いかに経済学者の描く最適行動など選択できるはずがない愚か者ということがよくわかる。
これからの経済学はアニマルスピリットをバグ扱いして軽視してはいけない。アニマルスピリットに注目し、せめて「予測できるエラー」といえるくらいの研究は必要なのだ。
「21世紀の資本」 (2013) トマ・ピケティ
r (資本収益率) > g (経済の成長率)
投資などの情報発信が流行っている昨今、上記の「貧富の格差拡大の原因を表すたった1つの式」を見たことがある人も多いのではないだろうか?
本書は「富の分配の格差の原因と対策」について書かれた本だ。
著者であるピケティの思想は、すべてこの「r > g」に集約させることができる。
rとは「資本収益率」。資本とは「富」あるいは「財産」のことで、その中心は金融資本(預金・株式・国債など)と工業資本(工場・機械など)になる。そしてそこから得られる収益(=資本所得)の率が資本収益率だから、つまり資本収益率とは「資本全体の価値に対する利潤・配当・利子・株の値上がり益・賃料などの割合」ということになる。つまり資本所得は「財産持ちの不労所得」と言い換えていいだろう。
これに対し、gは「経済の成長率」、つまり「1国が1年間に生み出した国民所得の、前年比での増加率」だ。ちなみに、国民所得は今見た資本所得に労働所得(国民が働いて得た収入)を加えたものだ。
ということは、「r > g」を大雑把に説明すれば「財産持ちの不労所得の方が、国民が働いて得た収入よりもかなり大きい」ということになる。
もしこれが事実なら、経済成長率が下がれば下がるほど、資産家と労働者の間の格差は拡大する。そして21世紀は世界的に経済成長が鈍化しつつある時代なのだ。
ピケティはこの「r > g」を「根本的な不等式」と呼ぶ。つまり、不労所得が賃金を大きく上回ることは大前提、変えようのない事実なのだ。
ピケティは格差をデータに基づき細かく分析し、その規模よりも「構造」、つまりその格差が「何から生まれたのか」をより重視する。そこで彼が注目したのが「資本所得、あるいは相続財産からくる格差」だ。
人口減少モード、資本の集中化と規模の経済、世界経済の収斂、スーパー経営者…etc.
21世紀の今日、格差拡大の条件はそろい、経済危機・低成長・人口の減少などで各国の財政は疲弊している。ここまで資本所得の弊害が出てくると、やらなきゃいけない政策もおのずと見えてくる。
ピケティが提案するのは、恒久的に課税する「世界的な累進資本税の創設」だ。
そもそもピケティは、格差そのものを否定しているわけではなく、「正当な格差」は容認している。平等な民主主義社会に格差はあっていいが、その格差は偶然の条件から生まれるものではなく、合理的かつ普遍的な原理によって生じるものでないといけない。
つまり、世襲の財産から生まれた格差は民主主義的にはダメで、「各人の努力の結果生まれた格差ならOK」という考え方だ。
しかも、その累進資本税は世界的なものでなければならない。なぜなら、今日の金融資本は思いっきりグローバル化しているからだ。せっかく自国で規制しても、それが他国で運用されたのでは話にならない。
ただしそれには、極めて高水準の国際金融の透明性と組み合わせなければならない。もちろん「タックス・ヘイブン(租税回避地)」の規制と透明化も含まれる。これは相当難しい。ピケティ自身も「空想的な発想」と言っている。
現状ではその実現には相当な困難が予想されるが、少なくとも取り組むことで、世界の資本主義は確実に民主主義に一歩近づくことができるのだ。
「善と悪の経済学」 (2009) トーマス・セドラチェク
まだ「経済学」というジャンルがなかった時代、この学問は「哲学倫理の一部」だった。
その頃に重視されていたのは「善悪」であり、人々は神話・宗教・哲学などの「物語」を駆使することで、その本質を理解しようと努めてきた。
ところが今日、経済学はいつの間にか「科学」になり、説明言語も科学にふさわしい「数学」になっていた。
だがここで素朴な疑問が湧き上がる。
はたして数学で人間の善悪を語れるのか?
これは確かに鋭い問いである。なぜなら、著者の言うように、経済学は基本的には「よい暮らし・よき人生」についての物語であり、どんな経済学説も結局のところ善悪を扱っていると言えるからだ。
そして、もし本当に経済学が善悪を主題とする物語ならば、数学で語れる部分などごく一部にすぎないことになる。セドラチェクはこの善悪を「経済学の魂」ととらえ、いつの間にか「魂のない肉体」となってしまった今日の経済学を「ゾンビ経済学」として批判する。
本書『善と悪の経済学』は、数学に魂を売ったことで、善悪の問題を切り離してしまった今日の主流派経済学への批判の本だ。
経済学者は経済学を科学として扱い、人間行動を始めとするすべての事象をモデル化して、数学的に解決しようとしてきた。
しかしこのやり方は、平時には機能しても危機時には機能しなくなることがわかってきた。
そうなると、「経済学の科学化」はその「代償」の方が大きくなる。それは「経済学から魂を抜き取ってしまった」ことだ。
経済学の魂とは「善悪」だ。意味や倫理や規範性だ。 魂を失った肉体はゾンビと化し、人間らしい感情を失ったゾンビはひたすら食って、別のゾンビを再生産するだけになる。
数学的な経済学では、愛情・友情・笑顔などのプライスレスな価値は測れない。
経済成長が当たり前だった時代なら、すべての人を物質的に満たすことで、倫理のなさをごまかせた。でももう、その大前提を崩すべき時期にきている。今や「常に成長しているのが当然」の時代ではなくなった。こうなると、突然みんなが不公平や不正義に敏感になり、倫理のなさが問題となる。
よく考えれば、かつての日本経済も道徳と強く結びついていた。
商人を擁護した江戸時代の思想家・石田梅岩は「売利を得るは商人の道なり」と説いているし、新1万円札の顔になる明治の実業家・渋沢栄一の著書は『論語と算盤』だ。
この2人に共通するのは義(正しい行い)と利(利益)を合わせた「義利合一」、つまり「義を通せば利益はおのずとついてくる」というビジネス倫理である。
もしも今の日本人が、この武士道精神と利益追求のハイブリッドな魂を忘れたせいで経済を停滞させたとするならば、今こそ「善と悪の経済学」に立ち返る必要があるのかもしれない。
そして、これは日本人だけでなく、成長の止まった世界経済にも言えることである。
「実践 行動経済学」 (2007) リチャード・H・セイラー
セイラーは2017年のノーベル経済学賞受賞者だ。
彼の専門分野は「行動経済学」であり、人間の経済行動に潜む「心理的側面」に注目する新しい経済学とのこと。学問領域としてはまだ新しいが、1990年代以降急速に発展し、今や主流派の経済学にひけを取らないほどに発展している。
今日の経済学は、科学たらんとするあまり、人間心理を軽視してきた。
いや、軽視というより単純化だ。
人間は、 市場で活躍するプレイヤーとして、 みんな自己の利益に忠実で、 合理的に判断でき、 周りにどんなノイズがあろうとミスも心変わりもせず、 常に冷静沈着に自己の効用(満足度)を最大化させる最適行動を選好する。
…現実社会にそんなエコノミック・ゴルゴ13みたいな奴はいない(笑)
人間には、やっかいなことに「心」がある。心は科学になじみにくい「主観の塊」であるうえに、しばしば人間の「行動」に影響を与える。
しかも、心は気まぐれで、弱く、周囲の状況や別の人間の心に影響されやすい。
これでは無理。経済学が科学になるのは不可能だ。
仮に百歩譲って、人間が本能と脊髄反射ではエコノミック・ゴルゴ13的な動きをする生き物だとしても、ぐらぐら揺れる僕らの心が、内面からゴルゴに不規則な行動を取らせる無数の触手を伸ばし、ついにはゴルゴをからめ捕る。
既存の経済学は、この「心の動き」を軽視しすぎた。これでは人間心理がもたらす、経済のセオリーから外れた数々の「例外事象」を説明できない。
でも幸いなことに、例外事象の多くには一定の「方向性」があり、「系統だっている」。
行動経済学は、人間の経済行動を心理面から考察し、そこから生まれるエラーが多数あることをまず「認識」し、それらを従来とは違ったアプローチで「補完」することを目指す。
本書で最も重要な言葉は「Nudge (ナッジ)」だ。「肘で軽く小突く」という意味で、相手の注意を引いたり、行動を促したりする時に使う。
また本書では、人間を「エコノ」と「ヒューマン」に分けて説明する。
エコノは「ホモ・エコノミクス (経済人)」からその名を取った「想像上の種」で、 合理的で自己の利益に忠実、頭脳明晰で強靭な意志を持つ、 市場経済のプレイヤーだ。 これに対してヒューマンは少々おつむが弱く、 状況と他人の言動に常に心を振り回されて非合理的な行動もとる、 「現実の人間」、つまり僕らのことだ。
世の人々が全員「エコノ」ならば、ナッジは一切必要ない。なぜなら、みんなほっといても最適行動を選択するからだ。
でも残念ながら、エコノは想像上の種、つまりそんな奴はいない。
ならば、間違いだらけの「ヒューマン」がやらかしそうな選択ミスを把握して、ナッジで軌道修正させてやるべきだ。
そう、本当に人々の幸せを願うなら、「選択の自由」は奪うべきではない。
でも、膨大な選択肢だけが提示されてアドバイザーがいないと、おバカな僕らヒューマンは間違えるかフリーズして何も選べなくなる。
ならば求められるのは、適切なナッジだ。
ナッジならば、押しつけでも禁止でもなく、人々の選択行動を誘導できる
行動経済学の実践を語る本書の原題が『Nudge』というのも納得いただけるだろう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここで紹介したのはおすすめ書籍でおすすめされた本の概要である(笑)
もっと知りたいと思ったら、本書にある分厚い経済学名著を机上にそっと立ててみよう(笑)
苦しみ楽しめ!!名著との格闘!!これぞ賢者への道程!!
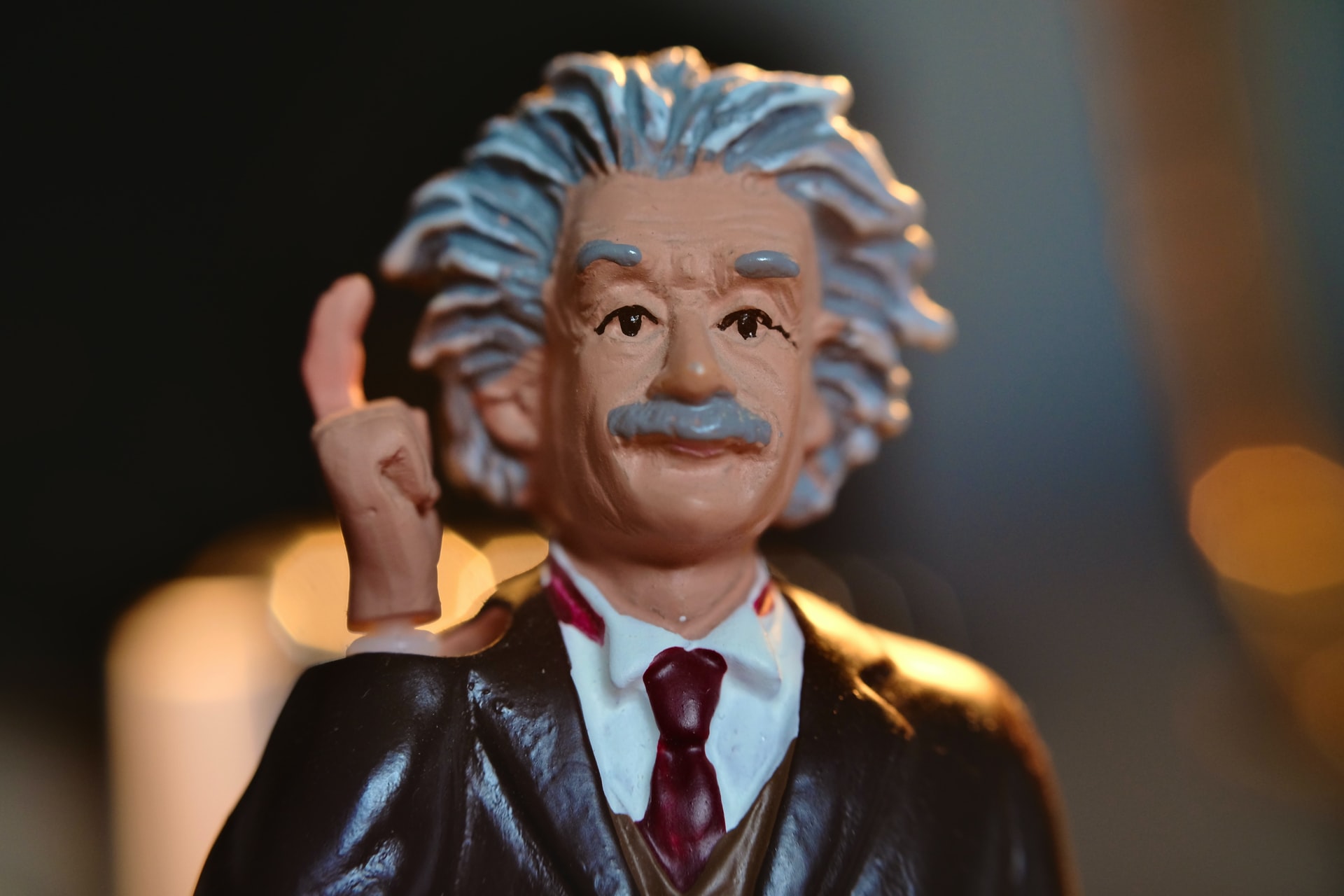


コメント