日本数学会の会員は約五千人、
大学にポストのある数学者はその半分くらいである。
学校で算数・数学を習ったことのない人は幼児以外にはいないであろうが、
数学者と個人的に話したことのある人はかなり少ないはずだ。
数学の研究成果がニュースに取り上げられることはめったになく、
数学者がどのような人たちかも一般にあまり知られていない。
奇人変人の代表例のように思われることも多い。
本書で数学研究とはどのようなものか、
数学者はどのように考え、どのように暮らしているのかについて、
多くの人にわかっていただけるとうれしい。
(本書「まえがき」より抜粋)
さてさてさて、前回・前々回に引き続き、おすすめ書籍↓からのトピックをば。
なおなお、このシリーズはまだ次回記事に続きます。
拝啓、もっと少ない記事数でちゃんとまとめろよ!!……ってお怒りの方へ。
面白いトピックが多くて、削りきれないんですッ!!(逆ギレ) サーセン(笑)


数学ジャーナル
数学のジャーナルは他の科学とはだいぶ違うことが多い。
まず数学の査読には時間がかかる。
論文を投稿した後に最初のレポートがくるまで半年かかるのは普通であり、
1年以上かかることもなんら珍しくない。
私はエディターとして迅速な査読プロセスを心がけているつもりだが、
それでもレポートを受け取るまで4年かかったという例がある。
国際電話をかけてレフェリー(査読者)に催促したがうまくいかずに、
レフェリーを何度も変えたりしていたのだ。
時間がかかるのは、数学の査読は正しさをチェックするべきだということになっているからである。しかし、数十ページの証明をきちんと読んで細部まで全部チェックすることは全く容易ではない。
その代わり、ちゃんと査読を通って出版されたものは永久に正しさが保証されているというのが建前である。
実際にはちょっと間違っている論文はたくさんあるのだが、それでもメジャーなジャーナルであれば、結論本体が間違っている論文はかなりまれである。
また、結論そのものが間違っている場合は撤回されるべきだということになっており、これもだいたいは守られている。
故に、数学では査読プロセスが正しさを保証するという公式見解はかなり維持されている。
実験ではないので結果の再現性が問題になるというようなこともない。
一部のトップジャーナルを除いて、数学のレフェリーは通常各論文1人なのだが、
これはちゃんと読んでくれる人を1人見つけるだけでも大変なのに、
もっと見つけるのはさらに大変だからということである。
これに関連して、数学者の論文の数は多くの科学分野よりかなり少なく、
論文1本の重みが大きい。
1年に1本書いていれば十分に立派な数字であり、
世界的な一流の数学者でも、もっと論文の数が少ない例はたくさんある。
他の自然科学と比べると、概して数学者の論文の数、引用の数はずっと少なく、
その代わりに1本あたりの著者の数が少なく、またページ数が多い。
たとえば、引用回数は10回あればけっこう良い数字である。
また共同研究が進んだ現在でも、半分くらいの論文は著者が1人だけであり、
著者の数が3人を超える論文はかなり少ない。
大学院生でも1人で論文を書くのはごく普通のことである。
長さについては、10ページ以下の論文はかなり少なく、
50ページ以上の論文もよく見かける。
ブログ主も何報か論文を書いているが、50ページという数字には驚愕せざるを得ない…。
プレプリントと数学
最近、常温常圧超伝導の論文とその検証論文が、
プレプリントサーバー arXivに大量に出て話題になった。
数学や理論物理学では何十年も前から、
出版もアクセプトもされていない論文のコピーを、
プレプリントとして同分野の専門家に郵送するということが広く行われていた。
これを電子化・一元化したのがarXivである。
1991年に物理学のプレプリントサーバーとして始まり、
1992年には数学も加わった。
どの論文も誰でも無料でダウンロードすることができる。
arXivという現在の名前になったのは1999年である。
私の論文は1997年に載せたのが最初で、
それ以来すべての論文はここに載せている。
現在、数学ではほぼすべての論文が、ジャーナル投稿と前後して、
あるいはそれ以前にarXivに投稿されていると思う。
試しに最高峰ジャーナル 「Annals of mathematics」 のウェブサイトを見ると、
21本の論文が現在印刷中としてタイトルが載っているが、
この21本はすべてarXivでプレプリント版を読むことができる。
(注:著者がエッセイ記事を投稿した2023年11月時点)
このように、数学では論文の内容は投稿段階から(あるいはそれ以前から)公開されているのが当たり前である。著者曰く、数学者の感覚から言うと、論文の公開時期を制限する制度であるエンバーゴなどまったく理解できない仕組みであるとのこと。
論文査読の仕組みには、レフェリー名を著者に隠すだけでなく、著者名もレフェリーに隠す「ダブルブラインド」というものがあり、採用している分野やジャーナルもある。
だが、数学ではほとんどの投稿論文がarXivに著者名付きで公開されているので、そんなことをしても意味がない。最近、数学でもダブルブラインドを導入すると言っているジャーナルがいくつかあるのだが、うまくいくようには思えない。
プレプリントというものに慣れていない分野の人は、未出版論文を公開して結果のプライオリティがどうなるのかに不安を感じることがあるようだが、誰もが見ているところに日付入で改竄不可能な形でプレプリントが公開されるのだから、arXivへの掲載でプライオリティは成立し、盗作することは不可能である。
論文がタダでプレプリントサーバーに載せられて、タダで読めるのなら、
高額のジャーナルは何のためにあるのだろうか。
実際、
全部プレプリントサーバーに任せてジャーナルをなくせばよい、
論文の価値判定はプレプリントサーバー上のコメントや引用回数に任せればよい、
…という主張をする人はいる。
しかし、内容の正しさや価値を判定するというジャーナルの役目の価値は、
現在でも下がっていないと思う。
昔から数学者が論文を読んだり引用したりする際には、
その論文が投稿、アクセプト、出版、どのジャーナルに掲載されているか、
…といったことはまったく気にしない。
中身が正しいかどうか、どのくらいの価値があるかは、
プロとして自分で判断すべきものだがらである。
たとえば、現在でもarXivには多くのでたらめ論文が載っているが、
みんな単に無視するだけである。
一方、採用・昇進・研究費採択・授賞などの審査の際には依然として論文がどのジャーナルに載っているかは大いに重要である。
数学ではインパクトファクターは全く重要ではなく、ジャーナルの格付けは数学者間で共有されている意識によるのだが、トップジャーナルに載っていればこれらの審査では強い。
審査員が論文の中身を自分で読んで判定すべきだということもよく言われるが、著者曰く、それは無理とのこと。
素晴らしい論文なのか、それとも、全くの無価値、でたらめなのかさえ、ごく少数の専門家以外にはわからないのが数学では普通のことである。
一方、数学のトップジャーナルに10年前に載った論文を今見てみれば、
間違っている、今では価値がない、正しいのかどうかわからない、
…といったケースはごくごくわずかである。
この意味でトップジャーナルでの正誤・価値判定は、
かなりきちんと行われており信頼度は高い。
十数年後にジャーナルのシステムがどうなっているか予見することは難しいが、
今と同じようにプレプリントサーバーと共存していくのではないかと考えている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
続きのトピック(シリーズ初回参考)は次の記事にて。まだまだお許しを(笑)
悩み迷え!! 数学者の思案(論文編)!! これぞ賢者への道程!!
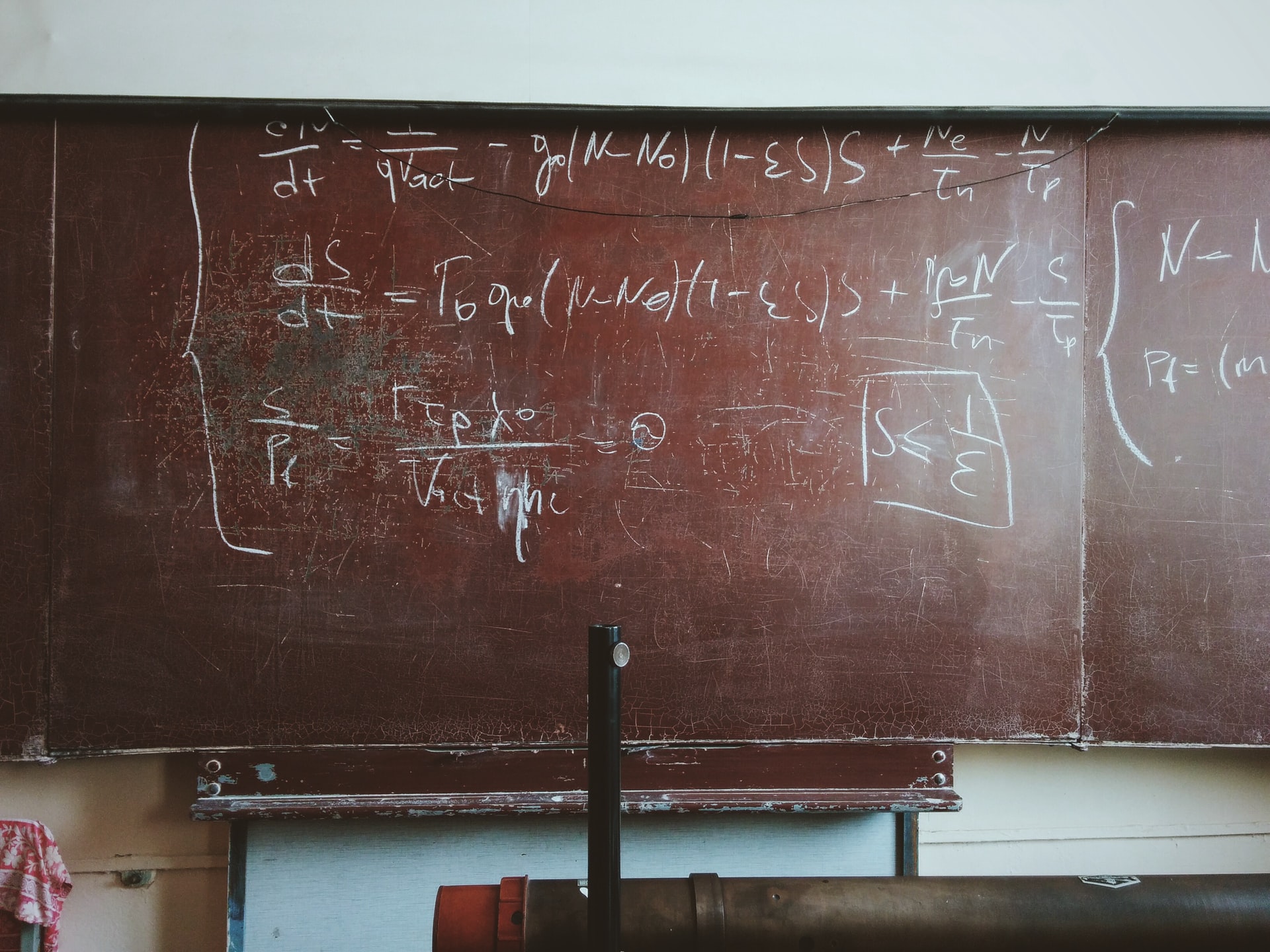

コメント