近年の脳科学の進歩によって、
脳の機能はかなり解明されています。
やる気。
集中力。
学習力。
記憶力。
想像力。
作業効率。
そうした人間の能力について、
脳のどの部分がどのように関与しているのか、
それぞれを高めるためには何をしたらいいのかということが、
かなり具体的にわかってきました。
私は精神科医として患者さんを診察するかたわら、
15年ほど脳科学研究に携わりました。
米国シカゴのイリノイ大学に3年間留学し、
セロトニンやドーパミン、
さらにはGABA (γ-アミノ酪酸/Gamma-Aminobutyric Acid) などの脳内物質が、
うつ病や自殺者の脳でどのように変化しているのかについて調べました。
その間、
たくさんの論文や本を読み、
いろいろと勉強しました。
ただ、私が携わっていた生化学や分子レベルの仕事というのは、
治療に役立つまでに10~20年もかかります。
気の遠くなるような仕事なのです。
私は日々の実験を続けるうちに、
「こうした脳内物質の知識を、
もっとすぐに役立てる方法はないのか…」
と思うようになりました。
例えば、
ドーパミンのモチベーションや動機づけに関する働き。
セロトニンの意欲や気分に関する機能。
ヒトや動物を使った研究や実験で裏付けられた脳科学的に確からしい知見。
こうした、
すでに解明されている脳内物質の基本的な働きを、
「ごく普通のビジネスパーソン」に知ってもらうことで、
仕事に画期的な変化が起きるのではないかと思うのです。
そのための具体的な方法を、
科学的根拠に基づいて身につけて、
仕事力をパワーアップしてほしい。
苦しい仕事が楽しくできるように変換し、
もっと楽な形で脳のポテンシャルを高めて、
効率的に仕事をこなしてほしい。
そうした思いから執筆したのが、
この『脳を最適化すればあなたの能力は2倍になる』です。
(本書「序章」より抜粋)
先日の大学入学共通テストを終え、本格的に受験シーズンに突入した方も多いだろう。
ブログ主も普通の人より多く大学受験をこなしてきたので、このシーズン特有のピリピリ感には理解があるつもりだ。
頑張る受験生たちに幸あらんことを祈る。
(完)
…
……
………で終われるか!!(笑)
さてさて、受験に限らずだが、「脳の能力」の使い方には様々なTips (秘訣,コツ)がある。
知りたい? 知りたい? (ピリピリ感に理解があるとか言いながら、煽っていくスタイル(笑))
そんな方々へ紹介するのは、日々の生活・仕事術・人生観に関するブログ主(が勝手に仰いでいる)メンター四天王の一角、樺沢紫苑先生の著書↓だ。
パット見では胡散臭いタイトル(失礼ですいません(笑))である本書の内容を一言で表すと、「代表的な脳内物質7つの取扱説明書」である。
①ドーパミン:幸福・快感に関連
幸福物質を自在に操り、モチベーションを上げまくれ!
②ノルアドレナリン:ストレス反応・交感神経に関連
「恐怖」と「プレッシャー」で仕事効率を上げろ!
③アドレナリン:交感神経に関連
「怒り」と「興奮」を味方に変える
④セロトニン:落ち着き・平常心に関連
「癒し物質」で、朝仕事の効率化と気分転換
⑤メラトニン:眠気に関連
「睡眠物質」で完全リフレッシュ
⑥アセチルコリン:記憶と学習・副交感神経に関連
「認知機能」と「ひらめき」を高める方法
⑦エンドルフィン:多幸感・恍惚感に関連
「脳内麻薬」を味方につける究極の仕事術
書籍では、それら特性を活かした具体的な仕事術を一つ一つ紹介しながらも、どれかに特化せずに、バランスよく7つの脳内物質を使ったTipsを実践していくことを推奨している。
それにより、理想的な脳内物質の状態が実現し、結果として脳と身体が「健康」となり、潜在能力を100%、あるいはそれ以上引き出せるというわけだ。
それではお待ちかね! それらTipsを全て紹介! ……してたら日が暮れる(笑)
そこで本記事では、上記の脳内物質に関してブログ主が思う意外な事柄を紹介していこう。
もっと基本的で重要なことを知りたいと思った方は本書を読まれたし。悪しからず。
ドーパミン:プロセスを変える「北斗の拳仕事術」
マンガ『北斗の拳』は、核戦争によって文明と秩序が失われ暴力が支配する弱肉強食の世界に現れた、伝説の暗殺拳「北斗神拳」伝承者ケンシロウ。その生き様を描いたハードボイルドアクションだ。
長いスパンで見れば「宿命のライバル・ラオウとの戦い」という大筋はあるが、短いスパンで見ると「ケンシロウが小さな村を訪れ、悪者に抑圧されている村人と出会い、そこを支配しているボスを倒して村人を解放する」の繰り返し。典型的な勧善懲悪ストーリーにすぎない。
それなのに、圧倒的におもしろく、読者を引きつけるパワーを持っているのだ。
その理由は、ドーパミンが説明してくれる。
ケンシロウは毎回毎回、村人を苦しめている小ボスを倒していきます。
その倒し方が実にユニークなのです。
「北斗百裂拳」
「北斗柔破斬」
「北斗残悔拳」
…etc.
このように、敵役を倒す必殺技が毎回異なります。
読者はどんな必殺技で倒すのかが気になって、
作品の世界に引き込まれていきます。
ドーパミンはマンネリを嫌います。
そして、「工夫」と「変化」を好みます。
『北斗の拳』の場合、倒す小ボスにも個性がありますし、
それを倒す方法にも工夫と変化があります。
だから、また次を読みたくなるのです。
例えば、似たような作業や単純な計算など、毎日続く同じような勉強や業務にウンザリし、マンネリを感じている人もいるだろう。目標を設定してドーパミンを分泌させようとしても (詳細は本書参照)、志望校や職種的にそれが難しいこともある。
そんなときは、「北斗の拳仕事術」を使ってみよう。
同じ仕事でも、いつもと違った方法・手段・アプローチを用いて、チャレンジしてみる。
そうすれば、たどりつくゴールは同じでも、その展開にワクワクハラハラする。結果としてドーパミンが分泌されるのだ。
プロセスに「変化」を入れるだけで、やる気も出てくるし、仕事そのものも楽しくなる。達成したときの満足度も大きくなるのだ。
ノルアドレナリン:「普通の食事」で作られる
食事のとり方によっても、ノルアドレナリンの働き方(本書参照)は変わってくる。
食事によって、集中力やワーキングメモリを高められるわけだ。
ノルアドレナリンの生成には、必須アミノ酸である「フェニルアラニン」が不可欠。
必須アミノ酸というのは、他のアミノ酸から生合成できない(流用できない)アミノ酸のことである。食事を通じて摂取していないと、やがて欠乏してしまうのだ。
肉類・魚介類・大豆製品・かぼちゃ・卵・乳製品・チーズ・ナッツ類…etc.
フェニルアラニンを含むものは決して特別な食材ではありません。
「普通の食事」をしていれば、不足するということはないはずです。
フェニルアラニンが不足するとすれば、
偏食や極端なダイエットなどで、普通の食事ができない可能性が高いです。
また、
フェニルアラニンからノルアドレナリンの生成をするためには、
「ビタミンC」も不可欠です。
ビタミンCが不足すると、原料のフェニルアラニンが充分にあっても、
ノルアドレナリンをうまく生成できなくなります。
ビタミンCは、
パセリ・ブロッコリー・ピーマン・小松菜などの緑黄色野菜や、
レモン・イチゴ・ミカン・グレープフルーツ・柿・キウイなどの果物に、
多く含まれています。
よくレモン百個分のビタミンCが入ったサプリやドリンクが売られていますが、
過剰なビタミンCは数時間で体外に排出されてしまいます。
一度にたくさんのビタミンCを摂取するのは意味がなく、
三度の食事から少しずつ摂取するほうがはるかに効果的です。
フェニルアラニンは、セロトニンの原料である「トリプトファン」とともに、「うつ病の予防や治療に効果がある」と説明しているインターネット上のサイトがたくさんある。
そのせいか、これらのサプリメントも売られているのだ。
だが、大規模な医学研究において、こうしたサプリメントがうつ病の予防や治療に有効だという報告は、ほとんどない。
また、フェニルアラニンのサプリメントを大量にとって、ノルアドレナリンがより多く生成されて、集中力が高まったという実験データもない。
フェニルアラニンが不足した状態では機能低下を起こすが、過剰摂取したからといって機能アップはしないのだ。
必須アミノ酸やビタミンは、食事から継続的に摂取するのが一番。
どのようなサプリメントよりも、バランスの良い「普通の食事」こそが効果的なのである。
アドレナリン:心臓がドキドキしたら「成功する」と思え
重要な会議やプレゼンテーションなど、日常生活でも緊張を隠しきれない場面がある。
緊張すると心臓がドキドキする。このドキドキが苦手な人も多いだろう。
「自分はアドレナリンが出すぎだ」と思うかもしれない。
だが、それを過剰に心配する必要はないのだ。
緊張とともに心臓がドキドキするときは、あなたが100%以上の実力を発揮し、「成功」する予兆なのである。
緊張すると心臓がドキドキするのは、
緊張という精神的な刺激によって、
「カテコールアミン」という物質が分泌されているからです。
カテコールアミンは、
心臓が弱った患者さんや、
心肺停止状態の患者さんを蘇生するときに投与する薬としても使われており、
心臓を動かす作用が非常に強い物質です。
アドレナリンもカテコールアミンの一種ですから、
アドレナリンが分泌されると、心臓がドキドキするのです。
重要な会議の前に緊張を感じていると、アドレナリンやノルアドレナリンが分泌される。
結果、集中力や筋力がアップし、心と身体は臨戦状態になっているのだ。
心臓がドキドキするのは、緊張の証拠というよりも「脳も身体も最高のパフォーマンスを発揮できる状態」と理解するべきなのである。
大事な会議などの前にドキドキしたら「いつもよりうまくやれる徴候だ!」と思う。
ピンチに陥ってドキドキしたら「ピンチを乗り越えられる徴候だ!」とポジティブに捉える。
「心臓がドキドキするのは、成功する証拠」
この言葉を、おまじない的に心の中でつぶやいてみよう。
脳内物質の働きを知っていれば、ドキドキや緊張も恐くないはずだ。
とはいっても、
あまりにもドキドキする場合や、興奮しすぎて頭がボーっとするなど、
緊張が強すぎる場合は、
「深呼吸」でアドレナリンをコントロールすることもできます。
「緊張したら深呼吸しよう」
こうしたことは、昔から言われています。
あなたも聞いたことがあるはずです。
しかし、おまじないや迷信の類と考え、実践していない人も少なくないようです。
実際には、医学的にも根拠がある「正しい緊張緩和法」と言えます。
心臓がドキドキし、極度に緊張した状態になったら、深呼吸をしてください。
(アドレナリンを抑える具体的な深呼吸の方法は書籍を参照されたし。)
セロトニン:「感動の涙」で活性化
「日光を浴びる」・「リズム運動」・「咀嚼」…etc.
セロトニン神経を活性化する方法は本書で解説されている。
この章では、その中でも一風変わった、セロトニン神経の鍛え方を紹介しよう。
それは「映画を観て、感動の涙を流す」ということだ。
意外に思った人も多いだろうが、「共感」とセロトニンは、非常に重要な関係がある。
ギリシャの哲学者アリストテレスは著書『詩学』の中で、
悲劇を見ることで心の中に溜まっていた澱のような感情が解放され、
気持ちが浄化される効果があることを指摘しています。
その感情の浄化を「カタルシス」と呼びました。
悲劇を見て、感動して、涙を流す。
この結果、非常にスッキリとした気持ちになることは、
映画やドラマなどで、私たちもしばしば経験するはずです。
『脳からストレスを消す技術』(サンマーク出版)等の著書を持つ有田秀穂先生は、
感動的な映画を見て涙を流すとき、前頭前野の血流がよくなり、
セロトニン神経が活性化することを明らかにしました。
泣く直前の「交感神経優位」の状態から、
実際に涙を流して「副交感神経優位」の状態に切りかわる。
つまり、神経的なリラックスと癒しが得られるのです。
有田先生は前頭前野を中心に、
セロトニンと深く関わり共感を生み出す脳の役割を「共感脳」と呼んでいます。
この共感脳を鍛えることが、セロトニン神経を鍛えることにもつながるのです。
その結果、人の気持ちを察する能力が養われ、コミュニケーションも円滑になる。
やがては本当の「癒し」が実現するでしょう。
我々も共感力を磨いていこう。
ミュージカルや演劇、テレビドラマやアニメ、小説でもいいだろう。
なかでも約2時間のまとまった時間で、登場人物の心理をしっかり描き込み、感情移入も感動もしやすい「映画」を、著者は共感力トレーニングの方法として薦めている。
メラトニン:「不老長寿の妙薬」としての顔
メラトニンは「睡眠促進物質」(本書参照)であると同時に、「細胞修復物質」でもある。
「老化防止効果」や「抗腫瘍効果」があることは、各種の研究で明らかにされているのだ。
まず老化防止効果としては、強力な「抗酸化作用」を有しています。
抗酸化作用とは、身体を参加する原因である「活性酸素」を処理する作用です。
結果として、アンチエイジングの効果が得られます。
活性酸素は動脈硬化の原因にもなります。
動脈硬化が進むと、
心筋梗塞や脳卒中などの心血管系の病気の発症リスクが大きく高まります。
活性酸素が除去されることは、動脈硬化の予防にもつながり、
心筋梗塞や脳卒中の予防にもなるということです。
抗酸化作用が強い物質としては「ビタミンE」が知られています。
このビタミンEの2倍もの抗酸化作用が、メラトニンにはあるのです。
よく「錆びない身体を作ろう」と言われますが、
メラトニンは身体を錆から守る効果があるのです。
メラトニンが夜間にしっかりと分泌されれば、
病気のリスクを減らし、老化防止に役立ちます。
また、メラトニンには、
「腫瘍増殖作用」「血管新生抑制作用」「DNA修復作用」など、
多彩な抗腫瘍効果が認められています。
わかりやすく言えば、メラトニンは体内の重要な「回復物質」なのです。
私たちは疲れたときに、
「体力を回復しよう」とドリンク剤を飲むことがあります。
ですが、ドリンク剤には興奮物質であるカフェインが含まれていますから、
無理に頭と身体を興奮させているだけです。
元気になったように錯覚させるだけで、
ちっとも回復にはつながりません。
そんなことよりも、
究極の回復物質であるメラトニンを分泌させる。
グッスリ眠るとともに、
病気にもならず身体を若々しく保つことにもつながる。
そんな素晴らしい奇跡のホルモンを、
私たちの脳は自分で分泌させることにができるのです。
逆に回復がうまくいかず、身体に限界がおとずれたのが「過労死」だ。
実際に過労死は、疲れがたまって死ぬわけではない。疲れが過剰にたまったとしても、心筋梗塞や脳卒中という病気が、突然起きるものではないのだ。
過労死の原因となる心筋梗塞、脳卒中などの発生率は、仕事の量や大変さと比例するのではなく、「睡眠時間の短さと相関する」という研究結果がある。
ある調査では、週40時間勤務で残業がない人は、平均7.3時間の睡眠をとっていた。これが残業時間月80時間、つまり1日あたり3.5時間だと、睡眠時間は平均6時間に減少する。さらに残業時間が月100時間(1日あたり4.5時間)になると睡眠時間は5時間しかなくなる。
仕事が忙しくて、残業が多くなり、帰宅時間が遅くなる。
そして、睡眠時間が充分にとれなくなる。
その結果として、睡眠中の修復が不十分となって、心血管系疾患リスクが高まるのだ。
夜勤労働と発がん率について関係を表わすデータもあります。
「月3回以上の夜勤労働を30年以上続けると、乳がんの発症率が1.5倍になる」
「月3回以上の夜勤労働を15年以上続けると、大腸がんの発症率が1.4倍になる」
…etc.
かなり忙しくハードに仕事をしていても、睡眠時間をきちんと確保し、
またグッスリとした眠り、睡眠の質も確保されていれば、
バリバリと働くことができます。
心も体も健康でいられるわけですね。
そのためには、「質の高い充分時間の睡眠」が不可欠です。
夜にメラトニンを分泌させて、きちんと睡眠をとることが、
健康のためにも非常に重要なのです。
アセチルコリン:「卵かけご飯と豆腐入りのお味噌汁」がひらめきを生む?
原料となる「レシチン」が不足すると、アセチルコリンが充分に生成されない。
アセチルコリンを活性化させるためには、レシチンをきちんと摂取することが大切なのだ。
脳によいと言われるサプリメントを摂取しても、
「血液脳関門」という脳の関所によってせき止められ、
脳に充分に移行しないことがよくあります。
ただ、
レシチンは脳内への移行性が高いため、
食事で摂取されたレシチンは脳に移行し、
アセチルコリンの原料になります。
ただし、
レシチンの入った食品を2倍とれば、
アセチルコリンが2倍作られるわけではありません。
必要量のレシチンが不足状態になると、
アセチルコリンが充分に作られない可能性があるので、
不足しないように注意しようということです。
こうしたお話は、他の脳内物質と食事のお話でもしましたね。
レシチンを多く含む食材は卵黄と大豆だ。穀類(特に玄米)、レバー、ナッツにも含まれる。
つまり、「卵かけご飯と豆腐入りのお味噌汁」といった古典的な日本の食材を食べていれば、レシチンはそうそう不足するものではないのだ。
また、レシチンには「乳化」という非常にユニークな作用がある。これは油を溶かす作用だ。
カレーに隠し味で豆乳を入れると、非常に味がまろやかになるのだが、油の浮いたスープに豆乳を入れると、表面の油膜がスープ全体に溶け出してなくなるのがわかる。大豆を原料とする豆乳は、レシチンが豊富なのだ。
レシチンはその乳化作用によって、
血管壁に付着したコレステロールを溶かして動脈硬化を防ぐ働きがあります。
肝臓の脂肪を分解するので、
脂肪肝を予防する効果もあります。
レシチンは、成人病予防にも非常に効果のある栄養素ですので、
積極的に摂取したいものです。
昔ながらの日本の食事をしていれば、
レシチンは日常的に補給されています。
ただ、
最近の若い人の偏食傾向を考えると、
不足している人もいるかもしれません。
注意したいものです。
エンドルフィン:「感謝」は最高の成功法則
自己啓発書を読むと、必ずと言っていいほど、
「成功者は感謝の心を忘れない」
「感謝の心を持つことこそ、最高の成功法則」
…といったことが書かれている。
なぜ「感謝の心」を持てる人が成功するのか?
その理由は、人に感謝するとエンドルフィンが分泌されるからだ。
人に感謝するときも、
人から感謝されるときも、
人間は幸福感を抱くのです。
NIH(アメリカ国立衛生研究所)の研究グループは、
ボランティア活動をしている人の脳は、
「報酬」を受けたときの脳と同じ活性パターンを示すことを、
MRIによる研究で明らかにしました。
確かにボランティア活動をする人は、
ボランティア活動をしない人に比べ、
モチベーションが高く、活動的で、
達成感や幸福感を強く感じています。
さらに心臓疾患の罹患率が低く、
平均寿命が長いのです。
その理由は、ボランティア活動によって、
エンドルフィンが分泌されるためであるという研究があります。
また、
感謝されるというのは、
人からほめられるのと同様に、
精神的な報酬です。
ドーパミンも一緒に分泌されます。
人に感謝する。人から感謝される。あるいは、人の役に立つ。人に貢献する。
そういう瞬間に「報酬系」の偏桃体が刺激され、ドーパミンやエンドルフィンなどの脳内物質を分泌させるように働くのである。
人に感謝すること、そして人から感謝されることが、成功を引き寄せることは、科学的にも裏付けられているわけだ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
筆が乗って「フロー状態」(本書参照)になったのか、過去一の長さの記事になってしまった。
長々と語ってしまい、サーセン(笑)
最後に、やはりこうしたシーズンに無理しがちな方々へ、本書の一節を送ろう。
本書を手にしたビジネスパーソンなら
「仕事力をアップさせること」や「仕事の効率化」を実現して、
バリバリ働きたいと思っているはずです。
ですが、
私は精神科医なので、
そうした働き方は推奨しません。
それよりも、
あなたには病気にならないでいただきたい。
脳を疲労させない。
「心の病」と「身体の病気」にもならない
健康な身体を手に入れる方法を知っていただきたい。
そう思って本書を書きました。
脳の仕組みにかなった合理的な方法で仕事をこなしていくことで、
「仕事でバリバリ働く」ことと「心と体の健康」の両方が手に入れられるのです。
無理して働くことは、
仕事の効率を下げることであり、
健康を害することなのです。
ぜひ、
本書の仕事術と生活習慣を実行にうつし、
あなたの日々の仕事と心と身体の健康に役立てていただきたいと思います。
(本書「さいごに」より抜粋)
改めて、戦う受験生たちやビジネスパーソンたちに幸あらんことを願う。
活用せよ!! 脳と身体の特性!! これぞ賢者への道程!!
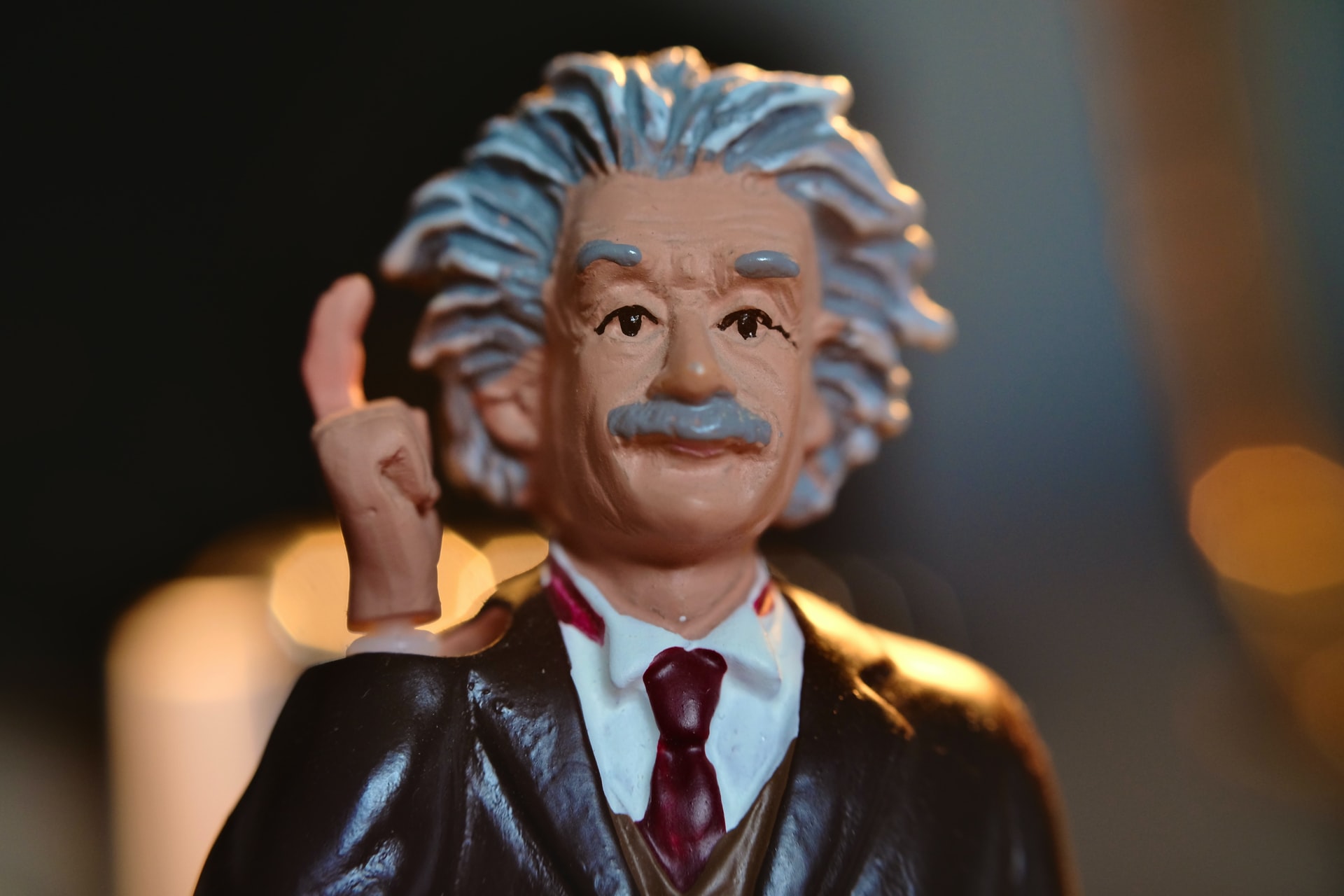

コメント