人間社会の研究を「社会学」という。 この学問は18世紀~19世紀頃、ニュートンの万有引力やダーウィンの自然選択といった重要な科学的発見の後に真面目に取り上げられるようになった。科学者や哲学者は、物理学世界と同様、人間・文化・人間同士の相互作用を科学的探究により理解することができないか考えていた。 社会学の父はフランスの哲学者でオーギュスト・コントで、彼は社会問題の答えは実証哲学のなかにあると信じていた。 現代の社会学は人々の間に形成される関係を基礎とし、その関係が層構造のネットワークを作り上げることで社会が成り立っていると考える。 今ではグローバリゼーションにより、この人間関係のネットワークが拡張していて、地球全体をカバーする一つの社会を作り上げている。 (参考:いつもの↓の文献。某名前を呼んではいけない人の分霊箱ではない(笑))
デュルケーム 「自殺論」、ハーバーマス 「公共性の構造転換」、ウェーバー 「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」など、世界の偉大な社会学者たちが世に発した名著の数々。
本記事で紹介する書籍↓(↑は釣りさ(笑))は、そんな名著50冊の要点をわかりやすく整理し、日々変化する時代の核心をつかむための「本物の教養」を提供してくれる一冊。
いわく、読むだけで「考え方」に差がつく!! いうねぇ(笑)
実はこの作者、前回記事(哲学の名著紹介)と同じ作者である!!
この本でも以下の章構成で、古典の傑作から新時代のベストセラーまで、著作の「時代的な背景」と「現代との関わり」も考察して内容紹介している。(毎度のブログ主の惨敗シリーズ(笑) 勝てる日はいつか来るのか?(笑))
① 社会学って、どんな学問? 「社会を考える学問」がわかる10冊
② ネット社会で人間は幸せになれるか? 「メディア・情報」を理解する10冊
③ 保守とリベラルの対立は続く? 「政治・権力」と「社会」の関係を紐解く10冊
④ 「民主主義」はいちばん正しい制度か? 「大衆社会」について読み解く10冊
⑤ 最先端の社会学者は今、何をかんがえているのか? 「現代の世界と日本」が見えてくる10冊
名著を解説した本をさらに解説するというのも(…以下略(笑)…)、ブログ主チョイスで「こんな考え方があるのか!」とハッとさせられた本を4冊ほど挙げよう。
「自殺論」 (1897) エミール・デュルケーム
社会学は若い学問だ。
「社会学」という言葉をオーギュスト・コントが使ってから、まだ200年も経っていない。学問として整備されるようになったのは、なんと19世紀末からである。
なかでも、社会学の重要性を社会にアピールし、「社会学主義」と呼ばれる立場を定着させたのは、エミール・デュルケームの功績である。そのため、「社会学」について知りたいと思い立ったら、何よりデュルケームの著作から始めるべきだろう。
さてさて、自殺は個人の問題か? 社会の問題か?
この書籍は近代社会学の礎となった古典的名著であり、社会学が取り扱うものとして「社会的事実」という概念を提示した。これは個人の外にありながら、個人を拘束するもので、「集合意識」とも呼ばれている。
社会的事実とは、 個人に対しては外在し、 かつ個人のうえに否応なく影響を課することのできる一種の強制力をもっている
では、個人の外に存在し、かつ個人に重大な影響を及ぼす社会的事実を、どのように解明できるのだろうか。
そのために要請されるのが、「方法論的集団主義」というものである。個人の意識ではなく集団の意識、つまり「集合意識」を分析する必要がでてくる。
この方法論的集団主義を実際の分析であきらかにするのが『自殺論』だ。
しかし、常識的に考えると、自殺はすぐれて個人的な問題ではないだろうか。それなのに、どうして社会的事実や集団主義がフォーカスされるのだろう。
例えば、デュルケームはカトリックとプロテスタントの人々を対象に、自殺率を比べている。そうすると、カトリックよりもプロテスタントのほうが自殺率が高いことがわかる。
あるいは、既婚者と独身者を比べてみると、独身者のほうが自殺率は高い。さらに、都市生活者と地方生活者を比べてみると、都市生活者の自殺率が高いわけである。
ここから次のように結論づけている。
自殺は、個人の属している社会的集団の統合の強さに反比例して増減する
ここで重要なことは、個人的な事象にみえる自殺が、社会集団の統合によって左右される点である。デュルケームは自殺を社会的統合と社会的規制の強弱で4つにタイプ分けし、方法論的集団主義を実証している。
詳細は割愛するが、この分類のなかで「アノミー的自殺」といわれるものについて注目しておきたい。この「アノミー」は『自殺論』のなかで最も有名になったキーワードだ。その後さまざまな人が使い、今では常識になった概念である。
「アノミー」というのは、ギリシャ語に由来する言葉で、「行為を規制する社会の規範が崩壊することによって引き起こされる無秩序状態」を意味している。
アノミーは、 現代社会における自殺の恒常的かつ特殊的な要因の一つであり、 年々の自殺率が現状のごとく維持している一つの源泉にほかならない
このようにみると、デュルケームが「社会学」を独立した学問として提示した理由も理解できるだろう。社会学でなければ、他の何がこれを示すのだろうか。
「監獄の誕生」 (1975) ミシェル・フーコー
2020年に新型コロナ感染症が世界的に流行したとき、カミュの小説『ペスト』とともに人々の念頭に浮かんだのは、ミシェル・フーコーの『監獄の誕生』だった。フーコーがペストと監獄との関係を描いたからだ。この書籍は出版から半世紀ほど経った今でも読み直されている、世界的ベストセラーである。
フーコーの著作を読むとき、前もって知っておくべきは彼の時代区分とテーマとなる時代だ。フーコーは17~18世紀を「古典主義」時代と呼び、それ以降を「近代」と語る。フーコーが主にテーマにするのは、古典主義時代から近代への移行期であった。
近代以前には残酷な身体刑が行われていたが、近代になると独房を中心とした監獄が確立した。そうした監獄を設計したのがイギリスの功利主義者ベンサムであり、それは「パノプティコン(一望監視施設)」と命名された。
中央の監視塔から全囚人を常に監視できるので、囚人は「監視されている」という意識をもち、規律正しい生活を送るようになる。こうしたやり方を、フーコーは「規律=訓練型の権力」と呼んだ。
フーコーが監獄をテーマにしたのは、監獄で見出される処罰の仕方が監獄だけでなく、家庭・学校・寄宿舎・工場・軍隊・病院といった、近代社会のさまざまなシステムで実施されているからだ。
近代社会はこうした閉鎖空間に人々を閉じ込め、 そこで絶えず監視することによって、規律=訓練を施している。 これが近代社会の「権力」だ。
それまで「権力」とは特定の人物や組織がもつ強制的な力とイメージされ、上から下に暴力的に働くと考えられてきた。
フーコーの権力論のどこが新しいかといえば、これを根底から覆したからである。権力という言葉で理解すべきは「無数の力関係」であり、権力は人間関係のいたるところで発生する。
人間関係のあるところには常に権力がある。 親と子、教師と生徒…いたるところに権力が見出される。
こうしてフーコーの権力論は権力の遍在論を導くことになる。
しかし、人間関係のあるところどこにでも権力があるとすれば、人間は権力から逃れることができないのだろうか。どうやって権力の外へ出ていくことができるのか。
フーコーが晩年まで問い続けたのはこの問題であった。
はたして、うまい答えが見つかったのだろうか。
「群衆心理」 (1895) ギュスターヴ・ル・ボン
フランス革命が終わり、19世紀に産業社会が発展し始めると、多くの人々が都市に集まり、労働者として働くようになった。その結果、労働運動も広がりをみせ、社会を動かす重要な勢力となり始めていた。
こうした状況を見て、1895年にいち早く「群衆の時代」と理解したのが、フランスの社会学者ギュスターヴ・ル・ボンである。
群衆の力を目の当たりにしてそれを政治利用したヒトラーの愛読書が『群衆心理』だったというのは、あまりにもできすぎた話である。だがたしかに、ヒトラーが利用できそうなフレーズが、本書には散りばめられているのだ。
まず確認しておきたいのは、個人が多数集合すれば「群衆」となるわけではないということである。「群衆」となるには、集団が個人の性質とは違った性質を備えなくてはならない。
「群衆心理」という集団の精神が生まれて初めて、「群衆」となる。 そのとき、意識的な個性が消え、個々人の感情や観念が「同一の方向」に向かう。 こうして現れるのが、「群衆の精神的統一の心理法則」である。
群衆心理の基本として注目すべきは、意識ではなく「無意識現象」が有力な役割を演じることだ。この点で、人々の知能や個性は消え失せるとル・ボンは考えている。無意識のレベルでは、すべての人が凡庸な性質をもち、同じようなものになってしまう。知能の違いなど、まったく問題にならないのだ。
群衆に特有な性質が出現する原因として、ル・ボンは3つの要素を挙げている。
1つめは「不可抗的な力」を感じること。つまり、自分では制御できない力が、自分に働くのである。そのため、「個人を抑制する責任観念」が完全に消え失せ、本能に任せてしまうとされる。一人だったらしないことでも、群衆になると平気で行動する。日常でもよく見かける光景である。
2つめは「精神的感染」と呼ばれている。これをル・ボンは催眠術と関連させている。精神的な感染が起こると、個人が集団の利益のために自分の利益を無造作に犠牲にしてしまうのである。あたかも催眠術にかかったかのように、感染してしまうのだ。この現象は、群衆の一員になるときでなければ、ほとんど起こることがないといわれる。
3つめの原因として挙げているのは「被暗示性」である。これは、2番目の「精神的感染」と関連し、その感染性は被暗示性の結果と考えられている。ル・ボンによれば、群衆の一員となれば、催眠術にかけられた人のように「意のままに操られる」。しかも、抑制できない行為をしようとする性急さは、群衆にあっては催眠術をかけられた個人よりも抑えがたい。
群衆中の個人は、自分の意思をもって自分を導く力のなくなった「一個の自動人形」
こうした個人の結集が、歴史の表舞台に登場し、20世紀を導く力となったのである。
「ブルシット・ジョブ」 (2018) デヴィッド・グレーバー
グレーバーは、アカデミックな研究者であると同時に、アナーキストの活動家でもある。彼は、私たちが通常は当然だとみなして疑うことがない現象を取り出し、興味深い例を用いながら問い直すのである。つまり、自明性を解体して、本質的な問題へと導くのである。こうして読者はハッとしながら、新たな発見をすることができる。彼の書籍がベストセラーになる理由も納得できるだろう。
誤解のないように最初に注意しておきたいのは、「ブルシット・ジョブ (クソどうでもいい仕事)」は、いわゆる3K (きつい・汚い・危険)と呼ばれる低賃金の仕事を指すわけではないことだ。では、「ブルシット・ジョブ」とはどのようなものだろうか。
例として、企業の顧問弁護士やロビイスト、保険数理士などさまざまな仕事を挙げている。しかし、これをみると基本的にはオフィスワークであり、総じて所得の高い仕事である。そのため、一般的には立派な職業のように感じられるのではないだろうか。それなのに、どうして「ブルシット・ジョブ」なのか、不思議である。
グレーバーによれば、「ブルシット・ジョブ」とは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完全に無意味で不必要で有害でもある、有償の雇用形態である。
他人が「ブルシット・ジョブかどうか」を判断するのではなく、 本人がどう感じているかが基準となるのだ
グレーバーの調査によると、オランダの労働者(なぜこの国をチョイスしたかは謎だが)40%が、自分の仕事の存在する確固たる理由はない、と報告したそうである。この割合を多いとみるか少ないとみるかは、意見が分かれるはずだ。
いずれにせよ、自分が今従事している仕事が「無意味であり、できれば存在しないほうがマシだ」と思っている人が存在するわけである。しかも、少数というわけではなく、50%近くの人たちがそう感じているらしいのだ。さらに衝撃的なのは、「所得の高い、オフィスワーカーに多い」ことである。
では、「ブルシット・ジョブ」に対して、どんな政策が必要になるのだろうか。
意味がないとしても、給料が支払われるので、問題ないように思えるだろう。実際、今までそのように考えられてきた。
ではグレーバーは何を目指すのだろうか。
もともとグレーバーの議論は1930年に経済学者ケインズが予測したことから出発している。
20世紀末までに、イギリスやアメリカのような国々では、 テクノロジーの進歩によって週15時間労働が達成されるだろう
これはテクノロジーの観点からいえば、「完全に達成可能」と考えられている。それにもかかわらず実現していないのは、「ブルシット・ジョブ」が増大化したからというわけだ。
だとすれば、肥大化した「ブルシット・ジョブ」を廃止すればよいのだが、そのような仕事から収入を得ていた人々の生活はどうなるのだろうか。
そこでグレーバーは「ベーシック・インカム (すべての人に所得保障として一定金額の現金を支給する制度)」を提唱することになる。
「ブルシット・ジョブ論」だけでは解決策は見当たらない。「ベーシック・インカム論」と向き合い、実践的な課題から検討していく必要があるだろう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここで紹介したのはおすすめ書籍でおすすめされた本の概要である(笑)
もっと知りたいと思ったら、本書を一読して、「社会学の今」を問おう、感じよう。
目指せ!!世の中を見抜く人!!これぞ賢者への道程!!
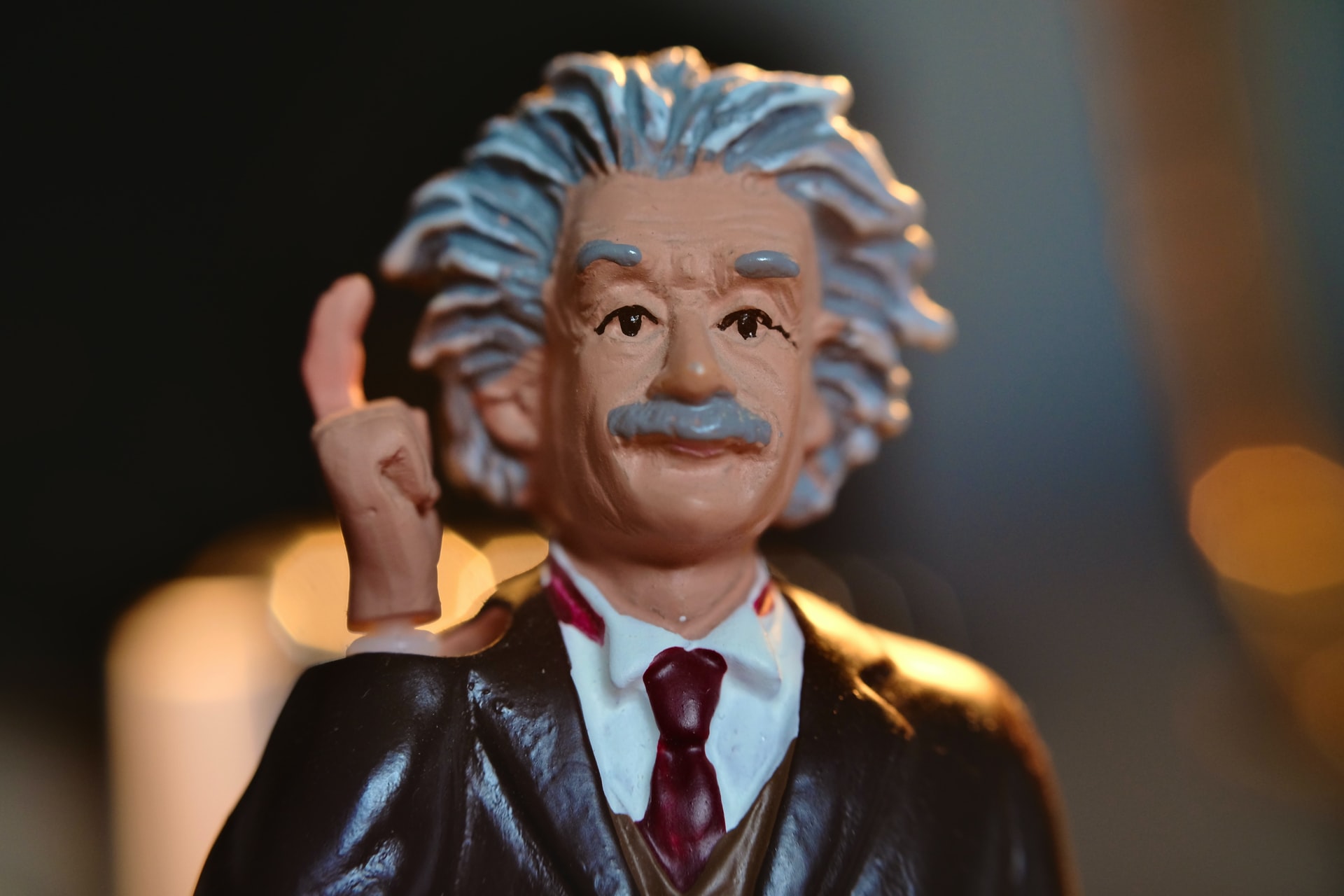


コメント